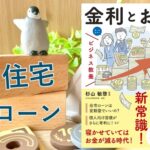日頃、私たちが目にするさまざまな商品や広告には、思わず購入したくなる魅力的なデザインが施されています。それらのデザインは、どのようにして生み出されるものなのでしょうか。デザイン界のトップランナーである野口孝仁氏が、“ビジネスにおけるデザイン”の新たな視点の見つけ方を語ります。
“ビジネスにおけるデザイン”を考えると、日本でも徐々にデザインというものが身近になってきているとはいえ、ヨーロッパなどと比べると、まだ発展途上といえる部分があるかなと感じています。
わかりやすい例でいうと、ヨーロッパ車はメーカーごとに見た目や性能が大きく異なりますが、日本車は異なるメーカーでも、そこまで大きなちがいはありません。デパートなんかも、目隠しして入店したら、多くの人がどのデバートに入ったのかわからないでしょう。また、これは仕方のない面もありますが、日本では、例えば起業をしたり、新事業を展開したりする際、重要とされるのは「集客」や「黒字化」などのセールス領域で、「世界観の構築」や「ブランディグ」などのような、利益に直結しないクリエイティブな領域は後回しになりがちです。
一方で、例えばオーストラリア発の、高品質のシャンプーなどを製造・販売しているあるブランドなんかは、最初に店舗を出した無名の段階から、店の空間や製品、広告にいたるまで、全面的にモダンでナチュラルな世界観をつくり上げていました。
さまざまな経営戦略がありますから、セールスを重要視する姿勢は、必ずしも悪いことではありません。ただ、早い段階からデザインの力を活用することで、「セグメントされた顧客に対し、ブランドの価値観や品質などを明確に伝える」という戦略は、永続的な事業の持続という意味では十分優位性があると思います。
もう1つ、“ビジネスにおけるデザイン”の力として感じるのは、理念や想いを明確にコミュニケーションできることですね。企業のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)などを社員へ浸透させるのに苦労をしている経営者は少なくありませんが、“企業の大切な想い”をシンボリックに表現したロゴをつくることで、「ロゴにはこういう意味がある」と社員にはっきりとスムーズに伝えることができます。
“他社にはない自社だけのアイデンティティ”を持つことは、社員が自社にプライドを持って働くことにつながるばずです。先ほど話したような、“他社とあまり変わらない”という状態では、自社に誇りを持つのはなかなか難しいのではないでしょうか。
昨今、ビジネスの世界でも “デザイン思考”という言葉を聞くことがあります。デザイン思考には幅広い意味があるのですが、私は、簡単に言えばデザイナーやクリエイターが、新しいアイデアを生み出す仕組みをメソッド化したものと解釈しています。
デザイン思考は、アイデアを「発散と収束」する思考法で、例えば、「春といえば?」と考え、「桜」「ピンク」「温かい」など無数にアイデアを発散させて、次にアイデアをグルーピングして収束させます。インタビューをしながらこれらを繰り返し、優れたアイデアの原液を抽出していくというメソッドです。
実際のデザインでいえば、例えば「エコの企画で新しいパッケージをつくります」となったときには、「大人の女性がターゲットになりそう」とか、「子どもっぽくならないためには〇〇〇が必要」とか、「ケミカルな印象を避けよう」とか、「そもそもエコならパッケージは必要なのか」など、深掘りしていきます。こうすることで、大事な情報、つまりアイデアの原液が浮き出てくるわけです。
デザイナーの立場で考えると、クライアントへのインタビューというか打ち合わせでインプットをしながら、アイデアを発散させていくというのは特別なことではなく、自然とデザイン思考を行っていることが多いと感じますね。というのも、コミュニケーションという面では、一般のビジネスパーソンはなにより「自社の想いを伝える」ことを考えますが、ユーザーに直接触れるものを生み出すグラフィックデザイナーやブロダクトデザイナーは、徹底的に「使う人や読む人」のことを考えます。
さまざまな観点から考えることでデザイン思考が習慣化され、アイデアを生み出すために重要な“新しい視点” を得ることができるんですね。この“新しい視点”を発見することこそ、デザイン思考の目的の1つだと思いますね。
私は長く雑誌のデザインをしていたことが、新しい視点を見つけるのに役立っていると感じますね。例えば、私がデザインをしていた雑誌の特集などでは、読書なら「読書特集」、ハワイなら「ハワイ特集」とはあまり言いません。「読書とコーヒー」や「大人のハワイ」など、キーワードを組み合わせて新しい視点をつくるんですね。この方法は、単純で誰にでもできますから、アイデアが必要なビジネスパーソンでも役立つと思います。
キーワードは、「時間」でも「場所」でも「国」でも、「最近気になっている言葉」や「身の回りの資料から拾った言葉」でもいいので、何かと組み合わせることで印象が大きく変わり、新しい視点が見つかりやすくなるはずです。「朝のコーヒー」と「夜のコーヒー」では、印象が全然ちがうようにね。
あとは、電車に乗ったときなど、乗客の格好や聞こえてくる音楽、読んでいる本、所作などをよく観察して暮らしを想像してみる、というのは私がよくしていることなんですが(笑)、デザイン思考の練習になるかなと。“観察”というのはインタビューと同じように、いろいろな情報をインプットすることができるので、実際にインタビューをする際に役立ちます。何より暮らしを想像するのはとても楽しいんです(笑)。ライダースジャケットを着ている人が、クラシックの音楽を聞いていたら、その意外性に興味を引かれませんか? 観察をすることで、インタビューやインプットの練習になりますし、「ライダースジャケットを着ている人はロックンロールを聴くもの」というような自分の思っている常識というか基準が崩されることがあるので、これまでの自分とは少し異なる新しい視点の発見にもつながると思います。
とはいっても、高い意識で取り組むとすぐ疲れてしまうので、無理のない範囲で、「楽しみながらできる」くらいの気持ちで取り組むと、ビジネスにも役立つし、日常の楽しみも増えるので、やってみてくださいね。
出典『サクッとわかるビジネス教養 デザイン』
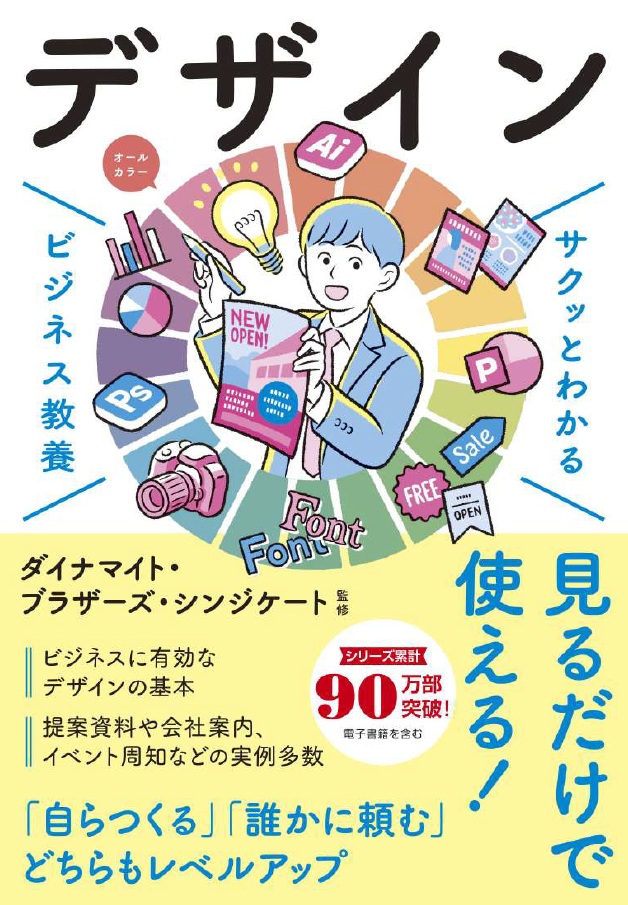
そこで、本書ではデザインの専門家などではなく、“デザインに触れる機会のあるビジネスパーソン”に向け、「デザインの前に考える」「デザインの要素」、「レイアウト」「意図とブラッシュアップ」という章立てで、デザインの基本的な考え方を紹介。「対象者や目的」にマッチしたデザインをつくれるようになるはずです。
最後にはデザイン界のトップランナーの1人である、ダイナマイト・ブラザーズ・シンジケートの代表を務める野口孝仁氏に“新しいアイデアの生み出し方”や“デザイン思考”についての特別インタビューを掲載しています。
現在では雑誌制作のなかで培ったトレンドを掴む感覚や編集思考、デザインの品質を武器に、各種ブランディング、百貨店のコンサルティング、店舗や商品のコンセプト開発など、 企業やサービスの価値自体をつくるクリエイティブへと変化している。「編集思考×アートディレクション」を軸に、上位概念から関わるものづくり、こだわり続けるデザイン力でこれからも新たな価値を創出している。
野口 孝仁/代表取締役社長。「Special Content」にてインタビューを掲載。著書の『THINK EDIT 編集思考でビジネスアイデアを発見するための5つの技術と10の習慣』(日経BP)や、『トップランナー』(NHK)に出演など精力的に活動。
井上ヒロキ/アートディレクター。全体の監修を担当。
植村 徹/プロデューサー/プランナー。本書の構成やプランニング、監修を担当。