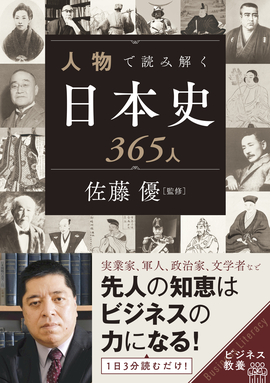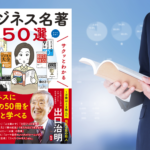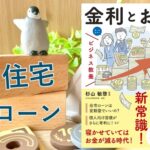2023年のNHK大河ドラマは、松本潤さん主演の「どうする家康」です。徳川家康、豊臣秀吉とともに「三英傑」の一人といわれる織田信長とはどのような人物だったのか? 『人物で読み解く日本史365人』(佐藤優 監修)から、学んでみましょう!
天下人となり、安土桃山時代を築いた武将。父は尾張下四郡を支配していた地方領主・織田信秀で、幼名は吉法師(きっぽうし)とつけられた。少年期の信長は好んで異様な風体をし、粗暴で奇天烈な行動をしていたことで、周囲から「大うつけ」と呼ばれていたという。そのため、生母の土田御前から疎まれ、後に家督争いで同母弟を暗殺することになる。
老臣の平手政秀が自刃することで信長の奇行を諫めたとする美談があるが、自刃の理由はほかにも「信長との不和」「家督争いにおける家臣たちとの対立」など諸説ある。
1546(天文15)年に元服し、父・信秀と敵対していた美濃国の武将・斎藤道三との和睦が成立したことで、道三の娘・濃姫を正室に迎える。その後、信秀が死去すると家督を継ぐが、「大うつけ」として信長を侮っていた一族の者たちが反発。そのため、一族内の敵対勢力を次々と鎮圧し、1559(永禄2)年に岩倉城主・織田信賢を追放することで尾張国をほぼ掌握した。
1560(永禄3)年、駿河・遠江・三河を支配する有力大名・今川義元が大軍を引き連れて尾張国に進攻。戦力的には大きく劣っていた信長だが、桶狭間で奇襲により義元を討つと、今川氏から独立した三河国の松平元康(後の徳川家康)と同盟を結び、東方の守りを固めた。そのおかげで美濃侵攻に専念できた信長は、1567(永禄10)年に井ノ口城を攻略して美濃国を支配する斎藤龍興を追放。井ノ口を「岐阜」と改称して新たな拠点とし、この頃から有名な「天下布武」の朱印を使い始めた。
「天下布武」は、従来の解釈としては「武力によって天下を支配する」「武家の政権で天下を治める」といった意味だと認識されていた。しかし、信長は「天下布武」の印判を他の大名に送った書状にも使っており、そんなことをすれば「宣戦布告」にとられかねないだろう。信長ほどの切れ者が、わざわざ敵を増やそうとしたとは思えない。
近年の研究では、当時の「天下」は室町幕府の将軍および幕府政治を指し、地域としては京都を中心とした五畿内(山城、大和、河内、和泉、摂津)を意味していたと考えられている。結果、信長の「天下布武」は「五畿内で室町幕府を再興する」という理念を宣言したものだったという見方が主流になっている。ただし、この説にも異論があり、今後の研究によって新たな真実が浮かび上がる可能性がある。
1568(永禄11)年、暗殺された室町幕府13代将軍・足利義輝の異母弟・義昭を奉じて上洛した信長は、義昭を15代将軍に就任させる。当初はそのことで信長を恩人と慕っていた義昭だが、信長が政治上の実権を握ったことで関係が悪化したため、各地の武将に呼び掛けて「信長包囲網」を形成した。浅井・朝倉両氏と戦った姉川の戦いで腹心の森可成(もりよしなり)を喪った信長は、浅井・朝倉両氏に協力した比叡山延暦寺を焼き討ちする。
この結果、1573(元亀4)年に戦国最強と謳われた騎馬隊を擁する武田信玄が進軍を開始。三方ヶ原の戦いで同盟を結んでいた徳川家康が大敗したことで絶体絶命のピンチに陥るが、信玄の急死により武田軍が撤退したことで一命を取り留めた。その後、信長は義昭を都から追放し、室町幕府を滅亡させたのである。
1575(天正3)年には、長篠の戦いで信玄の息子・勝頼を打ち破った。これまでは3千挺の鉄砲を用意し、「三段撃ち」で武田の騎馬隊を壊滅させたといわれているが、信長の人生を記録した『信長公記』にはその記述がなく、初出は江戸期の通俗小説とされており、真偽は疑わしい。しかし、当時の信長は貿易港であり鉄砲鍛冶が集まる商業都市・堺を支配下に置いていたため、織田軍は少なくとも千挺ほどの鉄砲を持ち込んでおり、これが当時としては異例の量だったのは間違いなく、画期的な戦術がなくとも物量で圧倒できたのではないかとする見方もある。
翌年には、近江国で安土城の築城を開始。1579(天正7)年に完成した安土城は、山城から平城への移行の形態を示し、五層七重の天守閣を備えた豪華絢爛な大建築だった。安土桃山文化を象徴する存在だったともいえる。
信長は南蛮文化への関心が強く、キリスト教の宣教師を保護。安土にセミナリヨ(小神学校)、京都に南蛮寺(教会)の建設を認め、宣教師の従者もしくは奴隷として来日した黒人男性を武士の身分に取り立て、「弥助」と名付けて身近に置いたという。
その一方で比叡山の焼き討ちや一向宗との衝突、自ら「第六天魔王」と称したことで、信長は「反仏教」であると見られてきた。だが、自身と敵対しない宗派については保護しており、キリスト教を仏教以上に厚遇したわけでもない。どちらかに肩入れするのではなく、フラットに宗教を見ていた可能性がある。
また、通行料を徴収するために設置していた関所を廃止して人の動きを活発化し、商品取引の拡大化と円滑化を促すために楽市・楽座を行うなど、経済政策にも力を入れた。
中国の毛利氏との決戦を前にした1582(天正10)年、京都・本能寺で明智光秀に謀反を起こされ、寺に火を放って自害した。享年49。光秀の謀反の理由は定番の怨恨説をはじめ、秀吉黒幕説、朝廷黒幕説、イエズス会黒幕説など諸説唱えられているがどれも決定打に乏しく、戦国時代最大のミステリーとなっている。
出典 『人物で読み解く日本史365人』
本記事は、上記出典を再編集したものです。(新星出版社/向山)
アイキャッチ画像 Shutterstock

1985年に同志社大学大学院神学研究科修了後、外務省に入省。在英国日本国大使館、在ロシア連邦日本国大使館に勤務。その後、本省国際情報局分析第一課で、主任分析官として対ロシア外交の最前線で活躍。2002年、背任と偽計業務妨害容疑で逮捕、起訴され、2009年6月に執行猶予付き有罪確定。2013年6月、執行猶予期間を満了し、刑の言い渡しが効力を失った。『国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』(新潮社)で第59回毎日出版文化賞特別賞受賞。『自壊する帝国』(新潮社)で新潮ドキュメント賞、大宅壮一ノンフィクション賞受賞。
『読書の技法』(東洋経済新報社 )、『勉強法 教養講座「情報分析とは何か」』(KADOKAWA)、『危機の正体 コロナ時代を生き抜く技法 』(朝日新聞出版)など、多数の著書がある。
🌟新星出版社からの近著…『死の言葉』
全人類に共通する「死」について、「知の巨人」佐藤優が歴史に残っている偉人たちの言葉をピックアップし、死生観について語っている。👉書誌情報ページ