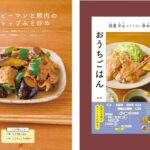個人事業主でも1人社長でも、事業をしている人は必ず、事業を行うための場所を設けているはずです。事業の種類によって、それは事務所だったり、店舗だったり、あるいは商品の倉庫という場合もあるでしょう。
それら事業専用の場所のために使った経費は、まず、ぜんぶ経費で落とせると考えていいでしょう。家賃はもちろんのこと、電気・ガス・水道、備品、事務用品――ぜんぶ経費で落とせます。
例えば冷蔵庫などは、家ではキッチンに置いてあるのでプライベートなものに思えます。しかし、事業のための来客に出す飲み物を冷やしているなら、これは経費で落ちます。
このように、専用の事務所、店舗、倉庫の場合は、ぜんぶ経費で落とせると考えられますが、問題は自宅兼用の事務所などの場合です。
個人事業主や1人社長のなかには、専用の事務所を構えるまでもなく、自宅兼事務所で仕事をしている方も多いでしょう。その場合、例えば家賃にはプライベートの費用と事業の経費が入り交じることになります。これらはきちんと分けて、事業の経費だけを取り出して計上しなければなりません。
そのためには、個人事業主ではこれを、「家事按分(かじあんぶん)」という方法で解決します。
つまり、個人事業主のプライベートと、事業の経費が入り交じった費用をそれぞれの割合で2つに分け、プライベートの分を取り除いて、事業の経費だけを取り出すのが、家事按分です。
一方、会社になっていると家事按分の方法は使えません。しかし、プライベートの分と事業の分を適切に分けて、事業の分を経費で落とす方法は考えられます。
このように、事務所、店舗、倉庫などに関連して発生する経費は、経費にあたるものだけを適切に計上することがポイントになります。
戸建てやマンションの自宅を維持するには、いろいろな支出が必要になるものです。当然、自宅兼事務所の場合には、いろいろな支出が経費で落とせます。自宅兼事務所で落とせる経費がないか、考えてみましょう。
マンションの修繕積立金
事務所の分については、経費で落とせます。勘定科目は「支払手数料」が望ましいでしょう。ただし、他の用途に使用しない、返還されないなどの条件があります。
マンションの管理組合に支払う管理費
事務所の分については経費で落とせます。勘定科目は「支払手数料」です。共益費も、同様に落とせます。
借家や賃貸マンションの更新料
事務所の分を経費で落とせますが、更新料の効果は契約期間全体に渡るので、支払った年に一括では落とせません。「前払費用」という資産の勘定科目を立てて、契約年数(最長5年)で少しずつ落とします。
火災保険料
例えば「5年の長期一括払い」をした場合も、更新料と同じ考え方で事務所の分を「前払費用」とし、5年間に渡って経費で落とします。
1年分を支払う場合は、契約期間が翌期に渡っても、1年以内なら今期の経費(「保険料」) で落とせます。
引っ越し代
事務所の分が落とせます。勘定科目は「支払手払手数料」です。
出典 『改訂3版
経費で落ちる領収書・レシートがぜんぶわかる本』
アイキャッチ画像 Shutterstock

あなたは、税金を払いすぎています!
本書を読めば、経費にできるモノ、できないモノがわかります!
インボイス制度にも完全対応!
【経費にできるモノがわかります!】
経費にできるモノの基本は「事業に必要かどうか」ですが、本当に認められるためには、そのことを「証明する」必要があります。
事業に必要なことをきちんと証明することができれば、それはすべて経費になります。
このことを知らずに、経費として処理できないモノが増え、結果、税金を多く払っている人は少なくありません。
本書では、どうすれば事業に必要なことを証明でき、経費として認められるかがわかります。
【インボイス制度にも完全対応!】
インボイス制度では、インボイスに登録していない事業主やお店で購入した場合、その消費税の一部が経費として認められません。つまり、買った側が損をしてしまうのです。
インボイスと認められるために必要なことや、インボイスとして認められない領収書を受け取ってしまったとき、また自動販売機での購入や割り勘なども、インボイス制度に合わせなければなりません。
本書では、このような、さまざまなインボイス制度への対応の仕方も解説しています。
また、インボイス制度には特例も多く、そもそも領収書やインボイスを必要としないモノもあり、これれについても解説しています。
【迷いそうな事例が満載!】
本書では、経費にできるのか、できないのか、按分するならどこまでなら許されるか? など、迷いそうな事例も多数挙げています。
たとえば、
・スマホ料金の注意点
・光熱費の現行引き落とししたときのポイント
・自宅を事業で使ったときに突っ込まれない按分
・SuicaやPASMOなどを使ったときの注意点
・クレジットカードを使ったときの落とし穴
・ボツになった企画の経費
・海外出張と海外旅行が交じっているとき
・プライベートと事業の経費のグレー部分があるとき
・電子帳簿法への対応
などの対応の仕方がわかります。
中央大学法学部法律学科卒。
優秀なビジネスマンや税理士を多数輩出する尾立村形会計事務所(東京都)で会計人としての修行を重ねる。
その後、関根圭一社会保険労務士・行政書士事務所(茨城県)にて、主に労働基準監督署や社会保険事務所の調査立ち会いや労使紛争解決等の人事業務、加えて、法人設立・建設業許可、遺産分割協議書や内容証明郵便及び会社議事録作成等の業務に携わる。
平成19 年には、共同で税理士法人ゼニックス・コンサルティングを設立。
現在は、学生時代から培った「リーガルマインド」を原点に、企業に内在する税務・人事・社内コンプライアンス等、経営全般の諸問題を横断的に解決する専門家として活躍している。著書に『個人事業と株式会社のメリット・デメリットがぜんぶわかる本』『個人事業を会社にするメリット・デメリットがぜんぶわかる本』(新星出版社)などがある。
👉 オフィシャルホームページ